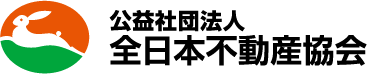【短期合格!】独学で宅建に合格する効率的な勉強法5選
2025年04月25日
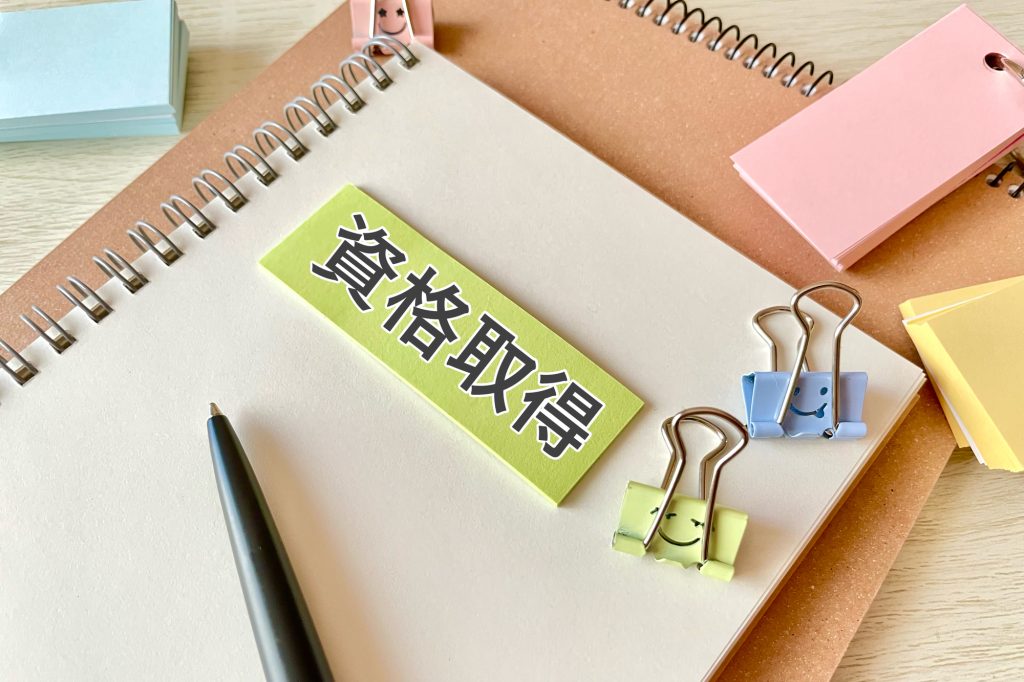
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引に関する国家資格です。合格すると資格保有者のみができる売買契約時の重要事項説明と、37条書面(契約書)への記名が実施できるなど、仕事の幅が広がります。資格の取得が顧客への安心感に繋がり、成約にも好影響があるでしょう。
本記事では、独学で宅建に合格する勉強法を5つ解説します。効率的な学習方法、独学で勉強するメリット・デメリット、独学で合格した人の体験談も紹介します。
宅建は独学でも合格できる?難易度や合格率を紹介
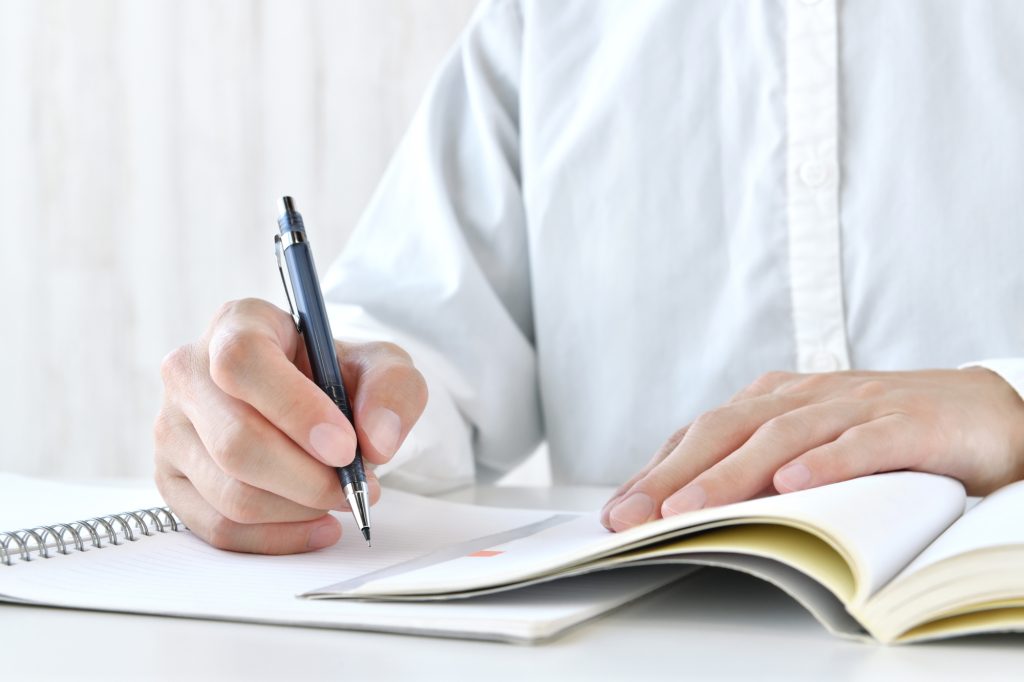
宅建士試験は、全50問の4択問題で、制限時間は120分です。出題分野は
- 民法
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 税・その他
4つに大別でき、マークシートで回答します。
※宅建業に従事し、登録講習を修了した「登録講習修了者」は、住宅金融支援機構・景品表示法・土地・建物・統計に関する5問が免除されます。
難易度は高く、令和5年度の試験の合格率は17.2%でした。平成26年度からの過去10年間の推移を見てみても、合格率はおよそ13〜18%。合格者は5~6人に1人です。
ブログやSNSの投稿、YouTubeの動画などでは、独学で合格した人の体験談も多く見つかります。学習方法によっては独学で合格できる資格と言えるでしょう。
◆関連情報:
宅建試験の概要|不動産適正取引推進機構
独学で宅建の勉強をするメリット

独学のメリットは、自分のペースで勉強できることです。講座を受講したり予備校に通ったりしていると、次の授業までに復習を済ませて、教わった内容を理解しておく必要があります。一方で独学は納得できるまで学習できます。早く学習が終わった項目に関しては、先取りで勉強しやすいのもメリットです。
金銭的な負担を抑えられるのも大きな利点です。講座や予備校を利用すると高額な授業料がかかりますが、独学は、参考書・問題集・過去問題集の費用のみで済みます。
独学で宅建の勉強をするデメリット
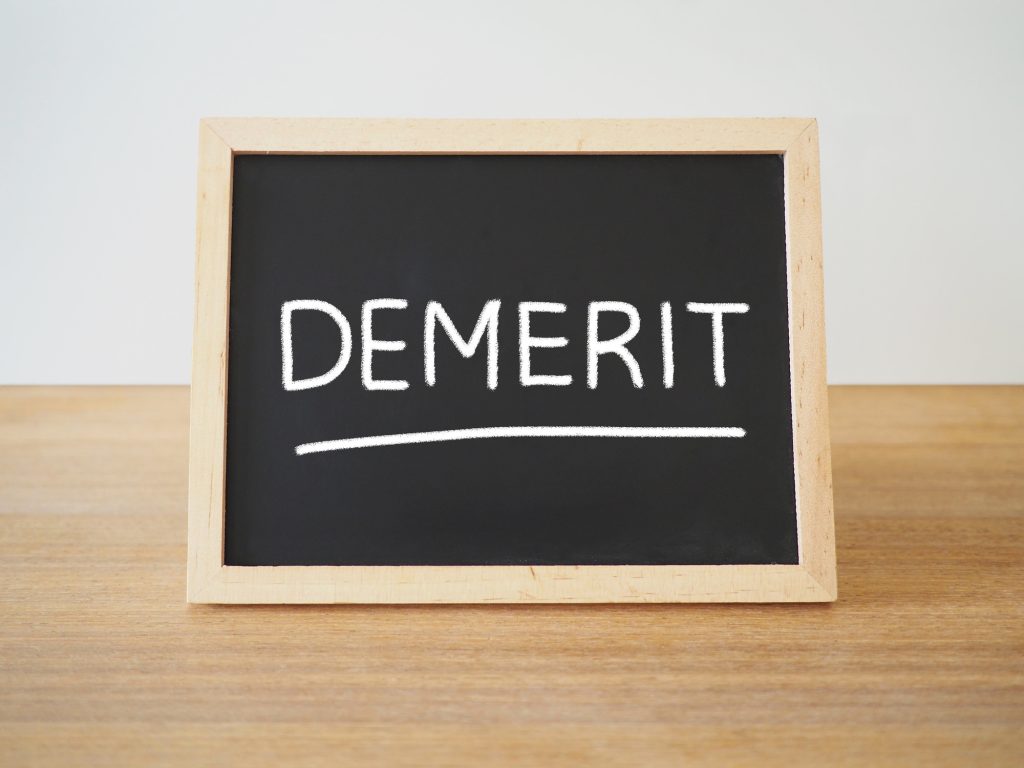
独学のデメリットは、学習内容が難しく理解に時間がかかることと、合格に重要なポイントが分かりにくいことです。
宅建は司法書士などの法律系資格を目指す人が入門として受験する国家資格です。初学者が問題文や選択肢を理解できるようになるまで時間がかかるため、はじめのうちは勉強の仕方が分からないかもしれません。
講座や予備校では、過去のデータや講師の経験をもとによく出題される項目やひっかけ問題などを教えてもらえますが、独学の場合はそのような機会がありません。
他の受験者の様子が分からず、モチベーションを維持しにくい点も挙げられます。「自分1人だと怠けてしまうかも」「周囲からの刺激を受けながら勉強したい」という方は、独学での学習には相当の覚悟が必要です。
宅建を独学で勉強する際のスケジュールの目安

宅建士試験は、毎年10月の第3日曜日に全国で一斉に実施されます。合格に必要な勉強時間の目安は200〜300時間程度、初心者の場合は500時間と言われます。試験日から逆算して、計画的に勉強を進めましょう。
初学者は平日に2時間、休日に6時間勉強し、勉強時間500時間で合格を目指す場合、遅くとも5月中旬から勉強を始める必要があります。直前1ヶ月は実際の試験を想定した演習と苦手な項目の復習に充てるため、9月中旬までにはすべての試験範囲を履修しておきたいところです。
宅建の合格につながる独学の勉強法を5つ紹介

宅建は合格率が20%以下と難易度が高い試験ですが、中には独学で合格する人もいます。効果が高い、独学の勉強法を5つ紹介しましょう。
1.章ごとにテキストを読んで演習問題を解く
テキストを1ページ目から最後まで全部読んだ後、演習問題を初めから解いていると、テキストの最初の方の記憶が曖昧になりがちです。学習内容を効率的に定着させるため、章ごとにテキストを読んで、その都度演習問題を解くようにしましょう。
「宅建業法」分野を例に挙げて説明します。宅建業法の問題は、保証協会・媒介契約・営業保証金と細分化されています。この場合、テキストで保証協会を学習したら、保証協会についての問題を解くようにしましょう。
インプットとアウトプットを同じタイミングで行うことで、学習内容を効率的に定着させることができます。
2.過去問題集を積極的に活用する
合格に欠かせないのが過去問題集です。分野別問題集を解いたら早めに過去問にチャレンジし、現状の理解度や出題の傾向を把握しましょう。おおよその把握が目的なので、制限時間より長い時間が掛かったり、合格点以下の点数を取ったりしても問題ありません。
間違えた問題はマークしておき、時間をおいて再度(何度も、できるまで)解くようにしましょう。
一般財団法人不動産適正取引推進機構の公式サイトでは、直近3ヶ年の問題と正解番号をダウンロードできます。解説はありませんので、過去問題集の購入は必須と言えます。
3.間違えた問題を重点的に解く
演習問題や過去問で間違えたところは、自分の中で十分に理解しきれていない項目です。どの部分をどう間違えたかを理解するため、ノートに書き出してみるといいでしょう。
間違えた問題にはチェックを入れ、もう一度テキストを読んで勉強し直します。少し時間を置いて同じ問題に取り組み、正解するまで同じ流れを繰り返すことで苦手なポイントを1つずつ潰していきましょう。
4.科目の優先順位を意識した勉強を心掛ける
宅建の問題数は全部で50問。大きく4つの分野(権利関係、宅建業法、法令上の制限、税・その他)に分けて出題されます。問題数が多く、配点が大きいところを重点的に勉強することが重要です。
配点が大きいのは、宅建業法と権利関係(民法)です。例年、宅建業法は20問、権利関係(民法)は14問出題されます。
宅建の合格ラインは50問中31〜38点です。宅建業法をきちんと理解すれば合格の可能性が高まります。
5.専門用語や暗記系の問題はアプリを活用する
宅建の試験には、不動産に関する専門用語が頻出します。知識として知っておけば解答できる問題もあるため、用語を覚えたり暗記系の問題の対策をしたりする際は、スマートフォンのアプリの活用がおすすめです。
アプリのメリットは手軽で、テキストやペンを用意する手間が省けることです。間違えた項目のみを抽出する機能や、解説付きのものもあるので、使いやすいものを選び、積極的に活用しましょう。
宅建を独学で勉強する際の時間の作り方を3つ紹介
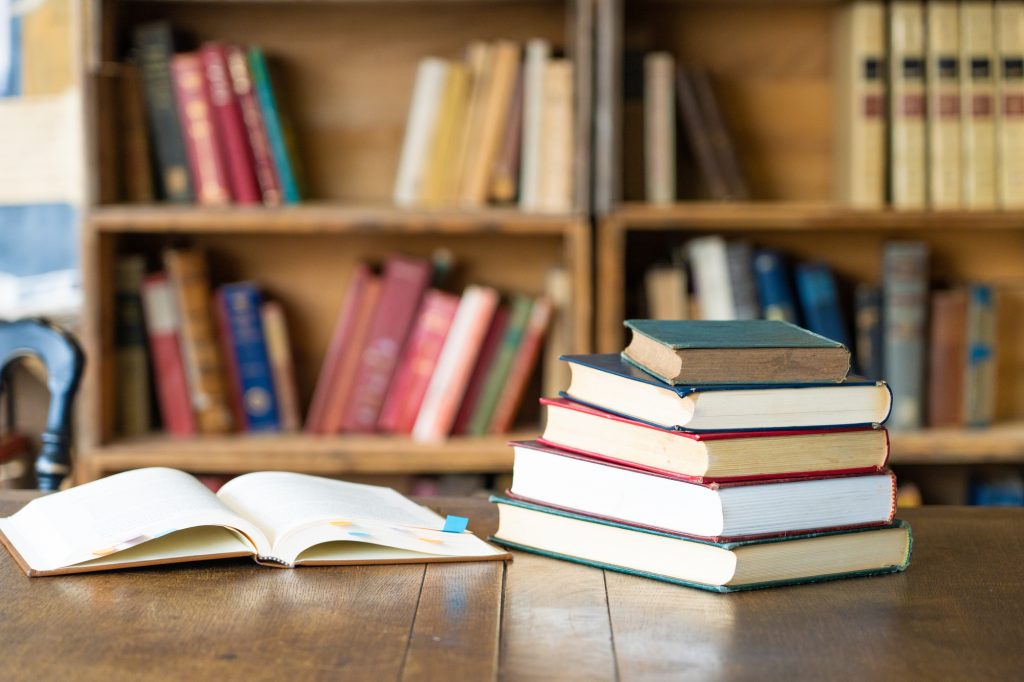
社会人になると、資格取得に向けた勉強時間の確保は難しいものです。講座や予備校へ通う場合、学習時間を強制的に確保できますが、独学の場合、そうはいきません。ここでは、宅建を独学で勉強する際の時間の作り方を3つ紹介します。
1.通勤・退勤時間や昼休みを活用する
勉強時間を確保したいときは、通勤・退勤時間や昼休みなどの「隙間時間」活用がおすすめです。コマ切れ時間を上手に使い、反復学習や用語の暗記をコツコツと行いましょう。
隙間時間の学習には、スマホアプリや分冊版の問題集の活用がおすすめです。
2.いつもより少し早起きしてみる
学習時間を確保するために、1〜2時間早く起床し「朝勉」してみるのもいいでしょう。朝は頭がスッキリしているぶん、勉強に集中しやすい時間帯です。帰宅後は仕事で疲れてしまうという方に「朝勉」は特におすすめです。
ただし朝の勉強時間を確保するため、睡眠時間を無理に削らないよう注意しましょう。6時間睡眠を2週間続けると、集中力や注意力が失われると言われています。適正睡眠時間の目安とされる7時間は、しっかりと睡眠時間を確保できるよう、スケジュール調整に気を配りましょう。
3.帰宅する時間を早めて勉強時間を確保
帰宅時間を1〜2時間早めるのもおすすめです。残業時間を減らす、飲み会への参加を控える、出勤時間やシフトをずらすなどして、試験勉強に充てられる時間を増やしましょう。
仕事や付き合いの関係で難しい場合があるかもしれませんが、差し障りのない範囲で帰宅時間を早めて、勉強時間を確保しましょう。
独学での宅建の勉強を成功させるために大切なポイント

独学は自分のペースで学習を進められる反面、周囲からの刺激を受けにくいため、モチベーションを維持しにくい側面もあります。独学での宅建の勉強を成功させるために大切なポイントを4つ紹介します。
1.いきなり完璧を目指さない
勉強をはじめたばかりの頃は解説の内容が理解できなかったり、演習問題を解いてもほとんどが不正解だったりするものです。宅建士試験は、法律系国家資格の入門資格でもあります。慣れないうちは問題文や設問の理解が難しいでしょう。しかし何度も読むうちに、徐々に意味がわかるようになります。いきなり完璧を目指さず、まずは毎日コツコツ勉強し続ける習慣をつけましょう。
2.モチベーションを維持する方法を見つける
独学の勉強は、「いまいち気が乗らない」「飽きてきた」など、モチベーションの低下がつきものです。自分なりのモチベーションを保つ方法を見つけて、試験当日までの限られた時間を有効に使いましょう。モチベーションを維持する方法の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- SNSで宅建を独学で勉強している人(同じ仲間)とつながる
- 定期的に自分へのご褒美を設ける
- 同業者との交流会に参加する
このように頑張っている人の存在を身近に感じたり、節目節目でリフレッシュする機会を設けたりすることで、モチベーションは保ちやすくなります
3.集中できないときは環境を変えてみる
いつも同じ場所で勉強していると、集中を欠く場合があります。自習可能なカフェや図書館に行くなど、環境を変えてみるのがおすすめです。
脳科学でも、場所を変えたり移動したりすることで記憶力が上昇する「場所ニューロン」なる概念が提唱されています。いつもと違う空間に行くことで脳が刺激され、集中力や学習意欲の回復が期待できるでしょう。
4.最新版のテキストや問題集を選ぶ
法改正等の影響により、過去問題の解釈が変わることは珍しくありません。独学で勉強すると、こうした最新情報のキャッチアップに疎くなる可能性があります。そのため、使用するテキストや問題集は最新版を選ぶようにしましょう。
宅建に独学で合格した人の体験談

ここでは、合格体験談を一つご紹介します。
介護職員のAさんは、約5ヶ月間独学で勉強して、50点満点中47点で宅建に一発合格しました。不動産の知識がまったくない状態からのスタートだったため、合格までに500時間以上かかり、1日の勉強時間は3時間、試験直前の1ヶ月間は1日4〜5時間だったそうです。
Aさんが意識したのは、
- テキスト・分野別問題集・過去問題集を1冊に絞り、繰り返し学習を行ったこと
- 配点が大きい宅建業法を完璧にしたこと
です。
また毎日以下のような流れで宅建の勉強をしました。
- 1.テキストを読む
- 2.YouTubeに投稿されている解説動画を視聴
- 3.演習問題を解く
- 4.翌日勉強する際は、昨日解いた問題をもう一度解いてから次の項目を学習する
宅建の問題を解説したYoutube動画も、何度も視聴したそうです。試験当日1ヶ月前までにテキストと分野別問題集を3周し、最後の1ヶ月は過去問に集中し、見事独学での合格を勝ち取りました。
宅建を独学で勉強するのが難しいときの選択肢

独学で宅建の合格を目指せる時間がない場合は、資格講座や予備校もおすすめです。昨今は大手資格予備校や独立系の講師によるWebスクールが人気です。
蓄積されたノウハウをもとに効率的に合格を目指せるカリキュラムが組まれているため、短い時間で宅建資格を取得しやすくなります。
費用は講座・予備校によって異なります。受講期間もスクールによって変わるので、自分に合うところを選んでください。
宅建は独学でも合格できる!効果的な勉強法を用いて学習を進めよう
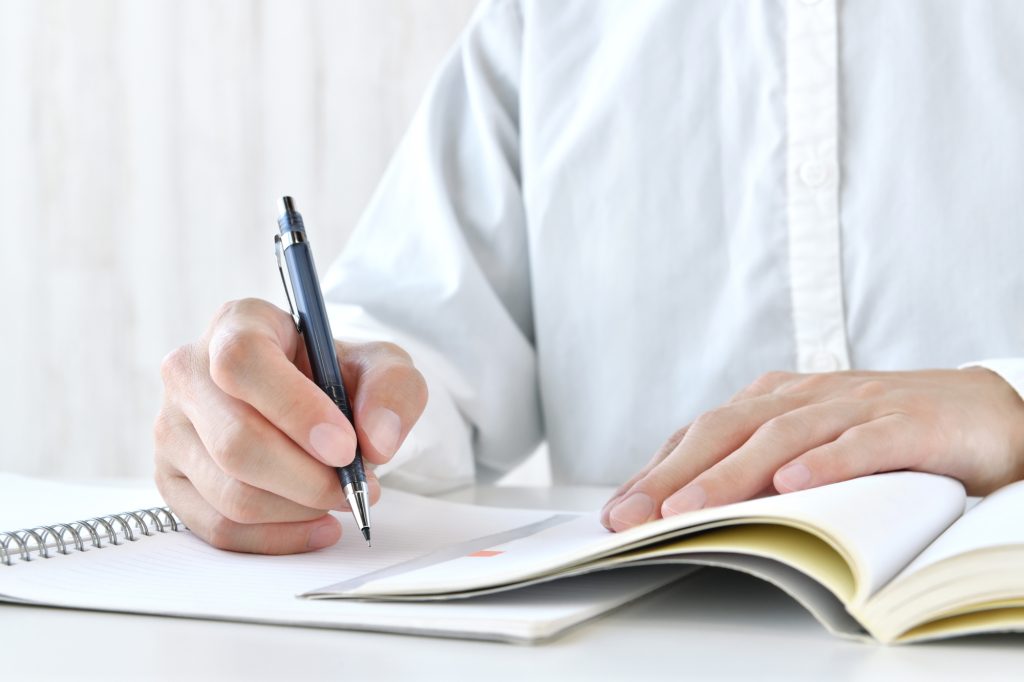
体験談で紹介したAさんのように、初心者でも独学で宅建に合格することは可能です。
宅建資格を取得することで、仕事の幅が広がったり、就職・転職・起業しやすくなったりします。宅建業法を優先的に勉強し、隙間時間を活用して、独学での宅建合格を目指しましょう。
不動産業開業のご相談は「全日本不動産協会」
「全日本不動産協会」は、1952年10月に創立された公益社団法人です。中小規模の不動産会社で構成されており、2025年2月末の正会員数は37,054社で年々増加しています。
不動産に関するさまざまな事業を展開し、調査研究や政策の提言、会員を対象とした研修などを行っています。47都道府県に本部を設置し、会員や消費者からの相談も受け付けています。
地域のネットワーク構築に、ぜひ全日本不動産協会をご活用ください。
カテゴリー
カテゴリー
最近よく読まれている記事
-
省エネ基準適合が住宅ローン減税の利用条件に!令和6年以降の【変更点】を解説
2024年02月19日
-
【2025年最新】不動産資格の完全ガイド|必須資格・おすすめ資格・選び方を徹底解説
2024年05月02日
-
【必読】不動産業の開業前に読んでおきたい!一人起業のトリセツ
2023年06月01日
-
2023年05月02日
-
外国人の不動産売買・購入に規制はある?|取引のポイントと注意点を解説
2025年03月13日