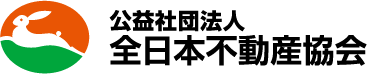賃貸不動産経営管理士試験とは|試験内容とメリットを解説
2025年09月19日
法改正・空室・孤独死対応・外国籍入居者支援など、賃貸不動産の経営にはたくさんの課題があります。
さらに、訪日観光客の増加に伴い注目される民泊の管理やルール整備も、不動産業界にとって重要なテーマとなっています。
本記事では、賃貸物件の知識を体系的に学習できる「賃貸不動産経営管理士」についてわかりやすく解説します。
「賃貸不動産経営管理士」とは

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務に必要な専門知識と実務能力を証明する国家資格です。
例年11月の第3日曜日に本試験が開催されており、令和6年度の合格者数は7,282名、合格率は24.1%。
宅建試験の約1カ月後で試験範囲も重なるため、不動産業に興味・関心を持つ人が多数受験しています。
国家資格になった背景
現代の日本社会は、空き家問題や高齢化、多文化共生、さらには孤独死といった深刻な課題に直面しています。
こうした複雑な課題に対応するには、法令に基づいた高度な知識と実務スキルを持つ専門家の存在が欠かせません。
その背景から、賃貸不動産経営管理士は賃貸人・賃借人双方の安心・安全を支えるプロフェッショナルとしての役割が期待され、国家資格として位置づけられました。
試験出題範囲
- 管理受託契約に関する事項
- 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
- 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
- 法に関する事項
上記に掲げるもののほか管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項 など
【参考】賃貸住宅に関する関連資格(宅建士・マンション管理士等)との違い
賃貸不動産経営管理士
賃貸借契約の管理、建物・設備の維持保全、金銭管理、長期修繕計画の策定等をオーナーへ提案するなど、賃貸不動産管理に関する専門的な知識を持ち、家主と入居者等に対し、公正中立な立場で職務を行います。
賃貸不動産経営管理士|一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
宅地建物取引士(宅建士)
不動産の売買・賃貸取引における重要事項説明・書面交付、契約締結を行います。
マンション管理士
分譲マンションの管理組合を支援し、スムーズな長期修繕計画、総会運営などをサポートします。
それぞれの分野を補い合うため、複数の資格を保有する「ダブルライセンス」や「トリプルライセンス」を目指してみるのも良いでしょう。
賃貸不動産経営管理士|試験の概要
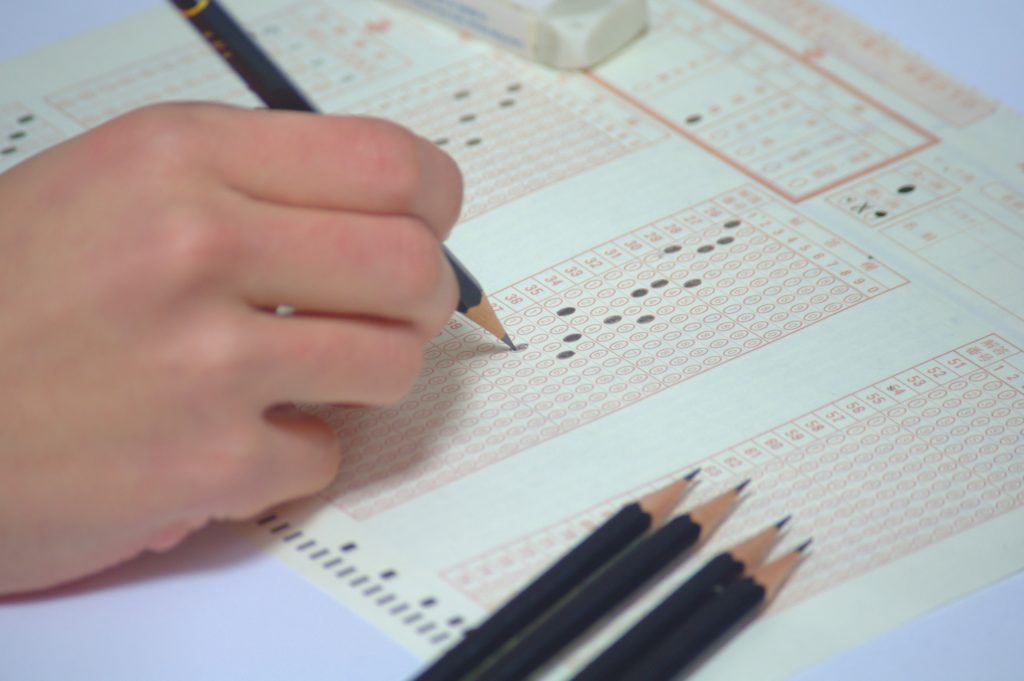
出題のポイント
賃貸不動産経営管理士の試験は、民法や建築基準法、税金といった宅建試験に重なる分野に加え、賃貸住宅管理に欠かせない賃貸住宅管理業法や、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインなども出題されます。
さらに、給水設備や排水設備といった建物設備の知識、長期修繕計画や維持管理に関する基礎も出題範囲に含まれています。これらは実務でのトラブル対応やオーナーへの提案に直結するため、学習しておくことで資格取得後の実務力強化にもつながります。
試験概要
受験は年1回、11月の第3日曜日に開催されます。
- 2025年(令和7年)は11月16日(日)13:00~15:00
- 4肢択一50問(120分)
- 受験料12,000円
- 講習修了者は5問免除(45問)
日本国内に居住していれば、年齢、性別、学歴等に制約はありません。
合格後、2年以上の実務経験または実務講習修了を満たすと、翌年度に資格が付与されます。
「賃貸不動産経営管理士」5問免除講習
5問免除講習の受講資格は、宅建試験のように宅建業に従事しているといった制限が設けられていません。
ただし近年の人気で、席が早めに埋まる傾向があるようです。例年、5月頃から申込を開始しているため、希望の場合は早めの申し込みがおすすめです。
賃貸不動産経営管理士協議会が指定する5問免除講習の実施機関
- 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
- 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会を含む)
- 公益社団法人全日本不動産協会(一般社団法人全国不動産協会を含む)
実務経験・講習と登録要件
実務経験2年以上
試験に合格した者で管理業務に関し、2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者等は、業務管理者の要件(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条)を満たします。
実務講習
eラーニング講習7時間+自主学習18時間、修了試験7割以上で合格。修了証の交付により「賃貸住宅管理業の実務経験2年を有する者と同等以上の能力」と認められます。
合格率・難易度と勉強方法
2024年度賃貸不動産経営管理士試験では、約3万人が受験して、合格率は24.1%でした。
この年の合格基準点は35問(5問免除者は45問中30問)です。
試験問題は市販の過去問題集よりも難易度が高い傾向があります。公式テキストを活用し、体系的な知識を身に付けましょう。
公式テキスト「賃貸不動産管理の知識と実務」
公式テキスト「令和7(2025)年度版 賃貸不動産管理の知識と実務」は、株式会社大成出版社から販売されています。
受験生は毎年春頃発売される最新版を使って学習しましょう。
令和7(2025)年度版賃貸不動産管理の知識と実務|目次
第1編 賃貸住宅管理総論
第2編 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第3編 契約の基礎知識
第4編 管理受託契約
第5編 賃貸借契約
第6編 金銭の管理
第7編 賃貸住宅の維持保全
第8編 管理業務の実施に関する事項
第9編 賃貸不動産経営管理士
引用:大成出版社公式サイト
賃貸住宅管理業法をはじめ、賃貸住宅の建物・設備等の維持保全、金銭の管理、賃貸借契約、その他の法令等を解説しています。
5問免除講習の教材としても使われているので、受験生はぜひご一読ください。
賃貸不動産経営管理士の配置義務と法的役割

業務管理者の配置義務・要件
賃貸住宅管理戸数200戸以上の事業者は、営業所又は事務所ごとに業務管理者を1名以上配置したうえで、国土交通大臣への賃貸管理業登録が義務付けられています。
【参考】業務管理者要件を満たすには
実務経験がある場合
賃貸不動産管理士試験に合格し、合格後1年以内に登録手続きもしくは登録講習を修了
実務経験がない場合
賃貸不動産管理士試験に合格し、実務講習および、登録手続きもしくは登録講習を修了
宅建士資格はあるが、賃貸不動産経営管理士資格はなく、実務経験がある場合
指定講習(10時間)を修了
宅建士資格はあるが、賃貸不動産経営管理士資格はなく、実務経験がない場合
実務講習・指定講習(10時間)を修了
賃貸不動産経営管理士が求められる理由
賃貸住宅のトラブル抑止
賃貸不動産経営管理士の配置により、業務の標準化や書類管理の精度向上が進み、業務の効率化が期待できます。
契約・更新・解約手続きや家賃管理などを体系的に運用することで、人的ミスやトラブルの発生が抑制されるでしょう。
今後の需要
少子高齢化や空き家問題、民泊規制の強化などを受けて、賃貸住宅管理の適正化がますます求められており、賃貸不動産経営管理士の専門性に対するニーズは拡大傾向にあります。
特に大手管理会社や分譲マンション管理組合、地方自治体の住宅支援など多様なフィールドで活躍でき、キャリアパスとしては管理責任者や相談窓口などの展開も可能です。
賃貸不動産経営管理士|取得のメリット
不動産管理業
賃貸不動産経営管理士としての知識やトラブル対応力を高めることで、オーナーや入居者からの信頼を得やすくなります。
契約獲得のチャンスが広がり、管理受託件数の増加も期待できるでしょう。
不動産仲介業
管理業務の専門知識が向上し、オーナーや入居者からの信頼獲得が期待できます。
契約・更新・退去といった賃貸管理の各場面で適切な提案ができるようになり、管理物件の受託拡大や新規顧客の獲得にもつながる可能性があります。
金融機関(保険・銀行)
不動産担保融資や保険引受時の物件評価・リスク分析に役立ちます。
賃貸経営や管理実務の知識を持つことで、オーナーや投資家への提案力が高まり、資産運用やローン商品、保険プランの提案に説得力が加わる効果も期待できます。
賃貸住宅オーナー
賃貸不動産経営管理士の資格を取得すると、入居者募集、契約、更新、退去、建物維持管理など一連の管理業務を、法令に基づき適切に行えるようになります。
管理会社任せにせず、自らの物件運営方針を的確に判断でき、不要なコストの削減やトラブル防止にも効果的です。
自主管理をしたい大家さんは、ぜひ資格取得をご検討ください。
大学生・専門学校生
賃貸不動産経営管理士の資格は、不動産業界や金融、建築への就職を目指す学生さんにもおすすめです。
賃貸不動産経営管理士の試験は、例年11月です。
10月に実施される宅建試験と重なる試験範囲も多いため、インプットした知識をそのまま試験に使えます。
ぜひ積極的に、資格取得を考えてみてください。
「賃貸不動産経営管理士」を取得し不動産業界でキャリアアップしよう!

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家であることを証明する国家資格です。
資格を取得すれば、オーナーや入居者からの信頼を得られるだけでなく、管理物件の受託拡大や新規顧客の開拓にも効果が期待できるでしょう。
不動産仲介・管理業務に限らず、銀行や保険会社、建築業界など多様な分野で評価されるため、就職・転職活動にも有利です。
専門性を高め、不動産業界でのキャリアアップを目指すなら、ぜひ賃貸不動産経営管理士の資格取得をご検討ください。
宅建業開業のご相談は「全日本不動産協会」
「全日本不動産協会」は、1952年10月に創立された公益社団法人です。中小規模の不動産会社で構成されており、2025年8月末の正会員数は37,721社で年々増加しています。
不動産に関するさまざまな事業を展開し、調査研究や政策の提言、会員を対象とした研修などを行っています。47都道府県に本部を設置し、会員や消費者からの相談も受け付けています。
地域のネットワーク構築に、全日本不動産協会をご活用ください。
カテゴリー
最近よく読まれている記事
-
省エネ基準適合が住宅ローン減税の利用条件に!令和6年以降の【変更点】を解説
2024年02月19日
-
【2025年最新】不動産資格の完全ガイド|必須資格・おすすめ資格・選び方を徹底解説
2024年05月02日
-
【必読】不動産業の開業前に読んでおきたい!一人起業のトリセツ
2023年06月01日
-
2023年05月02日
-
外国人の不動産売買・購入に規制はある?|取引のポイントと注意点を解説
2025年03月13日