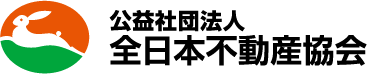競売物件とは?仕組み・メリット・リスク・購入の流れを徹底解説
2025年04月03日

競売物件は市場価格より安く購入できるため、一定の需要があります。
2024年の競売物件数は1万1,415件となり、前年比329件増加。これは2009年以来、15年ぶりの増加となります。
しかし占有者の立ち退き問題、物件の瑕疵、融資の難しさなど、競売特有のリスクがあり、取引の難易度は高くなります。
本記事では、競売の仕組みやリスク、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
★不動産業・宅建業にまつわるコラムどんどん更新中★
「競売物件」は3種類に大別

競売(きょうばい・けいばい)とは、債務者が契約通りに返済できない場合に、債権者が裁判所を通じて不動産を売却し、債務を回収するための手続きです。はじめに競売の種類を3タイプご紹介します。
強制競売
強制競売とは、税金の滞納や裁判での支払い命令に応じない場合に、裁判所の命令によって不動産が競売にかけられるケースです。住宅ローンや事業ローンの担保として不動産を設定していなくても、支払い命令に従わない場合は、債務者の不動産が差し押さえられ、競売にかけられることがあります。
担保不動産競売
担保不動産競売とは、住宅ローンや事業ローンの担保として設定された不動産が、債務不履行により競売にかけられるケースです。強制競売とは異なり、あらかじめ不動産が担保として設定されている点が特徴です。
形式的競売
形式的競売とは、法律上の手続きを満たすために行われるケースです。共有物分割や遺産分割に伴い、不動産を売却して現金化し、手続きを円滑に進める目的で実施されます。他の競売とは異なり、債務の精算を目的としていない点が特徴です。
競売物件の情報は「3点セット」で確認

競売物件の情報は、「3点セット」と呼ばれる3種類の書類で確認します。内容を簡単にご紹介します。
物件明細書
物件明細書とは、不動産の権利関係や法的な制約について記載された重要な資料です。抵当権や差押えの状況、賃借人の有無、占有者の引渡し条件などが明記されており、落札後のリスクを判断するうえで欠かせません。
特に「占有者がいる場合の引渡し条件」や「残置物の有無」は、競売物件の実際の使用や売却に大きく影響するため、慎重な確認が必要です。
現況調査報告書
現況調査報告書とは、執行官が現地調査を行い、物件の使用状況や占有者の有無、建物の構造・設備、周辺環境などを記録した報告書です。
写真や間取り図が添付され、物件の実際の状態を把握する際の参考になります。最も重要なのは、占有者に関する情報です。執行官の筆致から占有者の人となりを読み取り、判断に活かしましょう。
評価書
評価書とは、裁判所が選任した不動産鑑定士が物件の市場価値を評価し、適正な売却基準価額を算定するための資料です。土地の形状や接道状況、建物の築年数、周辺の取引事例、法的規制などを総合的に考慮して価格が決定されます。物件の瑕疵や特殊事情についても記載されるため、落札前のリスク分析に役立ちます。
競売物件の「金額」を3種類紹介

競売物件の取引では、「売却基準価額」「買受可能価額」「買受申出保証額」の3つの金額が重要な指標となります。概要を解説します。
売却基準価額
売却基準価額とは、競売物件の最低売却価格を決める基準となる金額で、裁判所が選任した不動産鑑定士の評価に基づいて算定されます。
市場価格や周辺の取引事例、物件の状態、法的規制などが考慮され、一般的には市場価格より低めに設定されるのが特徴です。ただし、実際の落札価格は入札によって決まるため、売却基準価額を参考にしながら適切な入札額を決定することが重要です。
買受可能価額
買受可能価額とは、競売物件が落札されるための最低入札額のことです。通常、売却基準価額の80%に設定されており、これを下回る入札は無効となります。
この基準は、競売手続きの公正性を保ちつつ、不当に低い価格での売却を防ぐ目的で設けられています。また、1回目の競売で落札者がいなかった場合、再競売ではさらに価格が引き下げられることがあります。
買受申出保証額
買受申出保証額とは、競売に参加する際に必要なデポジット(保証金)です。これは売却基準価額の約20%に設定され、落札した場合は売却代金の一部として充当されます。
落札できなかった場合は全額返還されますが、落札後に残代金を支払わなかった場合は没収されます。
競売物件を落札するまでの流れ
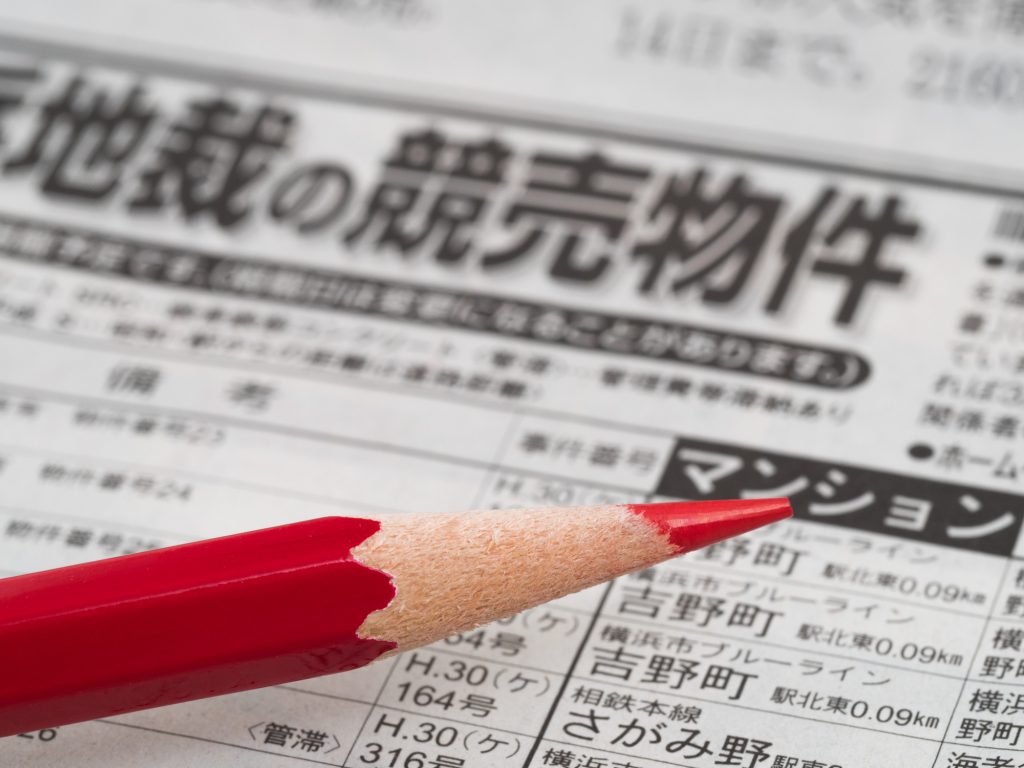
競売は、物件の取引の手順も通常の不動産売買とは異なります。競売物件を落札するまでの基本的な流れを解説します。
1.入札する競売物件を探す
はじめに入札する競売物件を探しましょう。競売物件は一般的な物件情報サイトには掲載されておらず、裁判所が運営する不動産競売物件情報サイトなどで検索します。
これらのサイトでは、入札期間・売却基準価額・土地面積・住所などの基本情報を確認できるほか、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)もダウンロード可能です。
2.競売物件に入札
入札する競売物件が決まったら、入札期間内に入札手続きを行います。入札時には、自分が提示する入札額の2割を保証金として納める必要があるため、必要な資金を事前に準備しておきましょう。
競売物件を落札した場合、事前に納めた2割の金額は売却代金の一部に充当されます。例えば、1,000万円で落札した場合、入札時に200万円を納め、落札後に残りの800万円を支払うことになります。一方、落札できなかった場合は、納めた保証金は全額返却されるため、安心して入札に参加できます。
3.競売の結果を確認
続いて、開札期日に競売の結果を確認します。競売物件はオークション形式で取引されますが、一般的なオークションのように同じ人が何度も入札して値段を上げる仕組みではありません。
入札で最も高い金額を提示した人が落札者となるため、入札は一度きり。金額を後から修正することはできないため、慎重に入札額を決定することが重要です。
4.代金支払い・裁判所で必要書類の提出
落札者には後日通知書が届くため、指定された期日までに残りの代金を支払う必要があります。支払えなかった場合、入札時に納めた2割の保証金は没収されます。
同時に、通知書・住民票・土地家屋の全部事項証明書・固定資産税通知書などの必要書類を裁判所に提出します。代金の支払いと必要書類の提出が完了すれば、競売物件の所有権を取得できます。
競売物件のメリット3点

競売物件ならではの魅力を3つご紹介します。
市場価格より安い
競売物件の最大の魅力は、市場相場よりも低い価格で購入できる点です。
一般的に、市場相場の5~7割程度の価格で落札できるケースが多いため、「少しでも予算を抑えたい」「広い家に住みたいが、予算に余裕がない」といった方にとっては、手頃な価格で物件を取得するチャンスとなります。
仲介手数料がかからない
競売物件は、不動産会社を介さずに裁判所を通じて直接購入するため、仲介手数料は発生しません。 そのため、一般の不動産取引と比べて仲介手数料分のコストを抑えることができます。
登記費用がかからない
競売物件の所有権移転登記は、裁判所の職権によって行われるため、通常の不動産売買のように司法書士へ依頼する必要がありません。
登記手続きを裁判所が進めてくれます。
競売物件を購入するリスクと対処法

競売物件は事情があるため、通常の不動産売買よりも高リスクです。具体的なポイントを解説します。
「内見」ができない
競売物件は基本的に「内見」ができません。そのため、事前に物件内部の状況を確認することは難しく、購入前に状態を把握するためには、「物件明細書・現況調査報告書・評価書」の3点セットを確認することが重要です。
ただし、これらの書類に記載された情報は、執行官や不動産鑑定士が調査した時点のものであり、実際に引き渡しを受けるときには、記載内容と現況が異なるケースもあります。
代金は一括払い
競売物件の代金は「一括払い」が原則です。落札後、裁判所が定めた期限内(通常は1~2か月程度)に全額を支払う必要があり、分割払いは認められていません。
自分が居住する場合は住宅ローンが利用できる可能性がありますが、審査が通らない場合も想定できます。
残置物の懸念
競売物件の所有権が落札者に移転した後、前所有者が家具や家電を置いたまま退去するケースがあります。
残された動産(家具・家電など)の処分は基本的に落札者の責任となります。しかし、前所有者の所有物であるため、勝手に処分するとトラブルになる可能性があります。
前所有者との交渉がうまくいかない場合は、裁判所への申立てや弁護士への相談を検討する必要があります。
物件に賃借人がいる
競売物件の中には、賃借人が居住するケースもあります。
落札前から賃貸契約が結ばれていた場合は賃借人の権利が借地借家法によって保護されるため、正当な理由がない限り退去を強制できません。
ただし対抗要件(建物の登記や賃貸借契約書の存在)を満たしていない場合は、落札者が退去を求めることが可能です。
落札後に賃貸契約が結ばれた場合は落札者の所有権が優先され、新たな賃貸契約は無効となる可能性が高いため、退去を求めることができます。
立ち退き交渉
落札後も前の所有者が住み続けている場合、落札者自身が立ち退きを依頼しなければなりません。
競売物件の取引は原則として落札者の自己責任となるため、不動産会社や裁判所が強制的に退去を支援してくれるわけではありません。そのため、立ち退き交渉が必要になる可能性があり、前所有者との対応を慎重に進める必要があります。
立ち退きを拒否された場合は明け渡し訴訟や強制執行などの法的手続きを取る必要が出てきます。こうしたトラブルを避けるためにも、事前に物件の占有状況をしっかり確認し、必要に応じて専門家(弁護士や競売に詳しい不動産会社)に相談することが重要です。
滞納管理費を請求される
マンションの競売物件の場合、前所有者が滞納していた管理費や駐車場代が請求される可能性があります。
特に管理費や修繕積立金は「マンション管理規約」に基づき、新しい所有者(落札者)が引き継ぐ義務を負うケースが一般的です。滞納期間が長い場合、数十万円~数百万円規模の請求になることもあります。
また極端に安い価格で出ている競売物件は、滞納管理費が考慮されている可能性が高いため、注意が必要です。
競売物件の取引は慎重に!

競売物件は、通常の取引よりも安く取得できる一方で、さまざまなリスクを伴います。
物件明細書・現況調査報告書・評価書の「3点セット」を確認し、綿密な資金計画を立てることが不可欠です。特に、占有者の有無や物件の瑕疵、追加費用の可能性を見極めた上で、慎重に判断することが求められます。
取引を検討する場合はリスクを理解し、適切な対策を講じましょう。
不動産や動産、債権などの差し押さえや競売のルールを規定し、強制執行を行う際の手続きを定めた改正民事執行法の詳細は、下記をご参照ください。
◆関連情報:
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について|法務省
全日本不動産協会が開催する、さまざまな研修もぜひご活用ください。
2025年の競売物件市場動向
2024年は競売物件数が15年ぶりに増加し、今後もやや増加傾向が続く見通しです。都市圏を中心に一戸建てやマンションが多く出品されており、長期金利の上昇や債務超過の増加が背景にあります
競売物件は、裁判所を通じて強制的に売却される不動産で、市場価格より安く購入できるチャンスがある一方、内見不可や瑕疵担保責任なし、明け渡しのリスクなど独自の注意点も多い物件です。購入を検討する際は、3点セットの確認や資金計画、法的リスクの把握、専門家への相談を徹底しましょう。
不動産業開業は「全日本不動産協会」まで
「全日本不動産協会」は、1952年に創立された公益社団法人です。中小規模の不動産業者で構成されており、2025年2月末時点の正会員数は37,054社にのぼります。
不動産に関する事業を幅広く手掛けており、政策の提言・調査研究・研修会の開催・法令改正の情報の伝達などを行っています。
全国47カ所に都道府県本部を設置し、会員や一般消費者に向けた相談事業も実施中です。競売物件に関するご相談も、ぜひ「全日本不動産協会」までお寄せください。
カテゴリー
タグ
最近よく読まれている記事
-
省エネ基準適合が住宅ローン減税の利用条件に!令和6年以降の【変更点】を解説
2024年02月19日
-
【2025年最新】不動産資格の完全ガイド|必須資格・おすすめ資格・選び方を徹底解説
2024年05月02日
-
【必読】不動産業の開業前に読んでおきたい!一人起業のトリセツ
2023年06月01日
-
2023年05月02日
-
外国人の不動産売買・購入に規制はある?|取引のポイントと注意点を解説
2025年03月13日