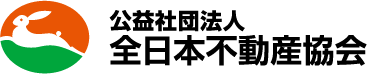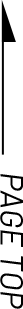税務相談
月刊不動産2012年10月号掲載
居住用不動産の譲渡に係る特例の適用要件である「居住の用」の判定について
情報企画室長 税理士 山崎 信義(税理士法人 タクトコンサルティング)
Q
居住用不動産の譲渡に係る譲渡所得の特例の適用要件である「家屋等が居住の用に供していること」を判定する際のポイントを教えてください。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
-
1.居住用不動産に係る譲渡所得の特例の要件
個人所有の家屋や土地の譲渡において、税の負担を軽減する特例を認める制度は少なくありません。それらの制度に共通して規定されている要件の一つは、その家屋や土地等が「居住の用」に供しているものであることです。
自身が高齢になって老人ホームに移ることとなった人、または、親の介護のために今まで居住していた家から親の家へ転居した、もしくは、そこをもう一つの生活拠点とした子が、今まで住んでいた家屋・敷地をとりあえずそのままにしておき、相当の期間が経ってから、その家屋・敷地を譲渡する場合、その時に至って、上記の特例を受けられないか…と考えることがあると思います。その場合、その家屋等を各特例に定められた一定の時点において、「居住の用」に供しているものであることが必要です。
2.「居住の用」に供しているかどうかの判定基準
所得税の特例の一つに、10年超所有の居住用の家屋等の譲渡に係る譲渡所得の金額に対する所得税の税率を10%に軽減する「居住用の家屋とその敷地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(租税特別措置法第31条の3)があります。この特例に関して、居住の用に供しているかどうかの判定基準を示す国税庁の通達(租税特別措置法通達31の3-2)が設けられています。
その通達は、居住用の家屋について「その者が生活の拠点として利用している家屋で一時的な利用を目的とするもの以外のものをいい、これに該当するかどうかは、その人や配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して」判定すると規定しています。この考え方は、「居住の用」という言葉の通常の意味に沿う常識的で妥当なものといえますから、この特例以外の各特例においても家屋が居住用に当たるか否かの判定の基本的な考え方として広く用いられるものです。
3.2の判定基準による判定の実際
2.の通達における「……日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定」する場合、具体的にどのような事実に着目されるのでしょうか。
そもそも「居住」とは、そこで日常生活を送って起居すること、寝起きすることですから、その家屋がそのために最低限必要な程度の大きさ・設備を備えていることが必要です。2.の通達でも、「その家屋の構造及び設備の状況」が考慮すべき点として言及されています。具体的には、その家屋に、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室が備わっていることが必須となります。
例えば、療養や介護が必要になった人が、その所有する自宅を出て病院や介護施設に入った場合を考えてみましょう。この場合の病院等は相部屋で、台所がない、必要最小限のもの以外の家財の持ち込みができない、トイレや浴室などが共同となっているはずです。その一方で、他の家族はその自宅に残り、その人の回復具合によって、いつでも自宅に戻って生活できるように自宅が管理されているのであれば、その人の「生活の拠点」となる場所は、病院等ではなくその自宅というべきですから、その自宅は「居住の用」に供されているといえるでしょう。
ただ、自宅が居住可能性を保ったまま残っていても、終身利用権が付いた老人ホームに入所している場合は、そこに生活の拠点を移したと考えるべきです。なぜなら、このような場合は、特段の事情がない限り、その入所の時点から、その自宅は「居住の用」に供しているとは言えなくなります。なぜなら、その家屋の構造及び設備が居住の用に十分なものであったとしても、そこに実際に居住していなければ、その家屋を居住の用に供しているものとは言えないからです。
そこで、家屋に実際に居住し、寝起きをしていた事実を主張するために最も説得力のある事実は何かということが重要になりますが、これは一般的に電気、水道、ガスの使用量の状況です。
電気、水道、ガスは、その家屋で寝起きしているという事実と連動してその使用が発生するものですから、これらの使用量等が通常の平均的な数値となっているかどうかが、その家屋における居住の事実と程度を測る有力なバロメーターとなります。