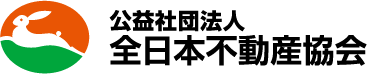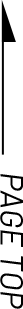賃貸相談
月刊不動産2007年4月号掲載
契約期間内の解約と残存期間の賃料の没収
弁護士 江口 正夫(海谷・江口法律事務所)
Q
当社は契約期間を4年とする建物賃貸借契約を締結する予定です。契約期間内に解約された場合には残存期間の賃料を違約金として受け取るつもりですが、こうした特約条項も有効と考えてよいでしょうか。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
-
1.賃借人による2種類の解約申入れ
建物賃貸借契約を賃借人が解約するには2つの場合があります。
1つは、賃貸借契約の期間を定めないで契約をしている場合の解約です。この場合は、賃借人はいつでも解約申入れをすることができ、解約申入後3か月を経過すると賃貸借契約は終了するものと定められています(民法617条)。この場合には解約した場合でも残存期間という概念自体がありませんので、解約に伴い残存期間の賃料相当額を違約金として没収するということがあり得ません。
もう1つは、賃貸借契約の期間を定めたにもかかわらず、契約期間内に賃借人が解約する場合です。例えば、賃貸借契約の期間を2年と定めているにもかかわらず、約束の2年の期間が到来していないのに契約の拘束から免れようとする場合です。この場合は、仮に10か月で解約した場合には1年2か月という残存期間の賃料をどうするのかという問題が生じます。ご質問のケースも4年間という期間を定めた賃貸借契約ですから、この残存期間の賃料をどうするのかということが問題になるわけです。
2.期間を定めた賃貸借契約の解約の可否
まず、そもそもの大前提として、契約期間を定めている賃貸借契約の場合に借家人は契約期間の中途で賃貸借解約を解約できるのか、ということが問題です。
例えばご質問の4年契約で建物を賃貸した場合は、賃貸人は、借家人に対して、賃貸借契約上、少なくとも4年間は当該建物を賃貸し続ける義務を負います。同様に、賃借人は4年間は当該賃貸借契約上は当該建物を借り続ける義務を負っているわけです。この場合に、契約期間の途中で解約するということは、当該建物を借りるということを合意した賃貸借契約に反することになりますから、原則として解約は認められてはいません。したがって、民法では、期間を定めた賃貸借契約を中途で解約できるのは、中途解約できるということを賃貸借契約の当事者が合意した場合だけと定められています(民法618条)。
一般に「期間内解約条項」とか「中途解約条項」といわれるものです。住宅の賃貸借契約の場合には契約期間を定めた場合でも1か月の予告をもって期間内解約できるという特約が設けられている場合が大多数です。住宅以外の事業系の建物賃貸借の場合でも6か月の予告をもって期間内解約できるとするものが多くみられますが、一部には、賃借人が期間を定めた賃貸借契約を期間内で解約する場合は、残存期間分の賃料額全部を違約金として支払わなければならないという特約を設けているケースもみられます。この特約が有効と解されるのであれば、賃貸人としては賃貸借契約期間中の賃料は、解約されるか否かにかかわらず確実に請求することができることになるのですが、この特約は必ずしも有効とは解せられていないので注意が必要です。
3.残存期間賃料没収特約の裁判での取扱い
賃貸借契約を契約期間内に解約した場合に、違約金として残存期間の賃料額を請求できるとする特約は、公序良俗違反として無効ではないか、また残存期間の賃料を全額請求するのは権利の濫用として認められないのではないか、ということが争われています。
裁判では、賃貸借期間を4年とした契約で、特約として「賃借人が期間満了前に解約する場合には、解約予告日の翌日から期間満了日までの賃料・共益費相当額を違約金として支払う」との条項を設けたものについて、賃借人が契約締結後10か月で賃貸借契約を解約したケースがあります。
裁判所は、賃料等の約3年2か月分を違約金として請求できるとする条項は、賃借人の解約の自由を極端に制約することになるから、その効力を全面的に認めることはできないと判示し、この特約は、賃借人が明渡しをした日の翌日から1年分の賃料・共益費相当額の限度で有効と解し、残りの部分は公序良俗違反として無効としています(東京地裁平成8年8月22日判決)。この判決の考え方は、期間内解約がなされた場合の違約金の額は、次のテナントを確保するのに通常要する期間分の賃料額等が相当であるとするものと思われ、相当期間は6か月~1年程度と考えられます。