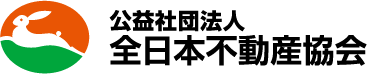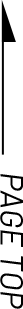税務相談
月刊不動産2011年4月号掲載
法人が土地と建物を一括取得した場合の取得価額の区分
情報企画室長 税理士 山崎 信義(税理士法人 タクトコンサルティング)
Q
法人が土地と建物を一括取得した場合における、税務上適正とされる取得価額の区分方法について教えてください。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
-
1.適正な取得価額の区分が必要とされる理由
土地と建物を一括で取得した場合、法人税法では、減価償却資産かどうか、消費税法では課税取引か非課税取引かどうかにより取扱いが異なります。
売買契約書上、土地と建物の取得対価が区分して明示されていない場合や、売買契約書上、土地と建物の対価が区分して明示されているものの、どうみても建物の対価が過大であって、合理的な区分ではない場合には、本来は土地の取得対価となる部分を建物の減価償却費に転換して損金とすることができることから、税務上の問題を避けるため、次の2.や3.の方法で、土地と建物の取得価額を合理的に区分する必要があります。
2.法人税法の取扱い
(1)基本的な考え方
法人税法においては、購入した減価償却資産の取得価額は、購入の代価に、引取運賃や手数料等といった諸掛(しょがか)り及び使用のために直接要した費用を加えて計算します。
この場合の購入の代価とは、原則として実際の取引で合意・成立した価額であり、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(これを「客観的交換価値」といい、土地の公示価格が代表例です)を反映した水準であるはずです。
ただし、実際には、売り急ぎ等の個別事情や当事者の主観的評価により価格が決められますから、必ずしも客観的交換価値と一致しません。その場合でも、通常取引の結果である限りは、客観的交換価値を求めてそれに引き直し、その差額は寄附金に当たるという認定は行われません。
上記の考え方より、契約書で土地及び建物の譲渡対価が区分されていない場合や、区分されていても合理的ではない場合には、税務上の問題が生じます。例えば、土地について路線価を基礎に公示価格に引き直したものを算定し、全体の譲渡価額から当該算定額を控除した残額を建物の取得価額とする方法は、一見良いように思えますが、全体の価額が客観的交換価値とはいえないなかで土地の価額だけを客観的交換価値とすると、建物の価額に主観的な要素の影響がすべて寄せ集められる結果となり、区分の方法として疑問が残ることになります。
(2)法人税法上、妥当とされる区分方法
①固定資産税評価額の割合による区分
法人税の課税の現場や裁判例などで比較的多く採用されている区分法は、一定の方法により算出した土地と建物の価額の割合によって、売買価額の総額を土地と建物に按分する方法です。その割合の基になる価額として、固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に時価を反映した合理的かつ統一的な評価基準で評価した価額であり、その入手の容易性・コストといった点でも優れていることから、一定の優位性が認められます。
②鑑定価額の割合による区分
上記①の方法は、固定資産税評価額は見直しが3年ごとであるため、取引時点とのズレが気になるケースもあり得ます。そのような場合には、費用はかかりますが、土地と建物につき不動産鑑定士による鑑定を行い、その鑑定価額の割合で按分することが、基準の同一性・時価の反映等の点で問題が生じない区分方法といえます。
3.消費税法の取扱い
(1)土地と建物を一括して売却した場合の取扱い
土地と建物の一括売買において、土地の時価に比べて売買契約書上の土地の譲渡対価がかなり高く、契約書上の建物分の対価が不当に低くなっている場合には、建物の譲渡に係る消費税額は過少となり、税務上の問題が生じます。
このように、土地と建物の各譲渡対価の区分が合理的でない場合は、譲渡時の時価の比で譲渡対価の総額を按分することが必要となります。
(2)土地と建物を一括して取得した場合の取扱い
上記(1)の取扱いにより、税務当局によって一括売却した売手側で消費税の過少分を更正された場合、買手の側でその更正額に相当する仕入税額控除の追加が行われるかどうかは、明らかではありません。また、買手が売買契約書上の税込譲渡対価の総額は変えないまま、独自に合理的な区分を主張して契約書上の消費税額と異なる消費税額の控除を行った場合についても、税務上の取扱いが不明確です。
土地・建物の一括取得にあたっては、取扱い不明な事態を招かないよう、買手・売手で十分に協議を重ね、合理的に対価を区分した売買契約書の締結に努めるべきです。