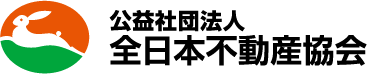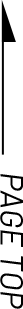法律相談
月刊不動産2009年1月号掲載
成年後見人による居住用不動産の売却
弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所)
Q
成年後見の審判を受けている高齢者につき、成年後見人が、本人に代わって居住用の不動産を売却するには、法的な制約があるでしょうか。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
-
成年後見人が、成年後見開始の審判を受けている高齢者に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
さて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人などの請求により、後見開始の審判をすることができます(民法7条。以下、民法の条文について、単に条文だけを掲げる)。後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とされ、成年後見人が付されます(8条)。
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表するのであり(859条1項)、成年後見人には、包括的に成年被後見人の財産を処分する権限が与えられています。したがって、成年後見人は、成年被後見人(以下、「本人」という)の不動産について、自らの判断によって売却できるのが原則です。
ところで、成年後見の制度の目的は、事理弁識能力を欠く本人を保護することにあり、成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(858条)。居住環境の変化は、精神医学の観点から、本人の精神状況に大きな影響を与えますから、居住用不動産を売却する場合には、特に本人保護への配慮が必要です。そのために、民法は、成年後見人が本人の居住用不動産を売却するに際しては、家庭裁判所の許可を要することとしています(859条の3)。
ここで居住用不動産に当たるかどうかは、本人の住民票があるかどうかなどの形式的な基準だけではなく、本人の生活実態が判断材料とされます。実際上、高齢者の場合、施設に入っていたり、病院に入院したりしていて、処分の時点では対象不動産に居住していないケースも少なくありませんが、居住用不動産とは、①本人の生活の本拠として現に居住している建物とその敷地、②現在居住していないが過去に生活の本拠となっていた建物とその敷地、③現在居住していないが将来生活の本拠として利用する予定の建物とその敷地のいずれかに該当するものをいうとされており、現在居住していない不動産であっても、居住用不動産に該当する場合もあります。
居住用不動産売却が許可になるか否かは、①売却の必要性、②本人の生活や看護の状況、本人の意向確認、③売却条件、④売却後の代金の保管、⑤親族の処分に対する態度などの要素が判断材料となります。
まず、①売却の必要性については、多くの場合、生活費や療養看護費の調達目的で売却がなされますが、その場合には、本人の財産状況として売却を必要とするのかどうかが問題とされます。②本人の生活や看護の状況としては、入所や入院の状況と帰宅の見込み、本人の意向確認がなされます。帰宅する場合の帰宅先がどのように確保できるのかは、審理における重要な要素です。③売却条件も、相当なものでなければならず、また、④売却代金が、本人のために使われるよう、売却代金の入金や保管についても、チェックされます。⑤本人の推定相続人など、親族が、処分に対して反対していないかどうかも、大事なポイントです。
これらの要素を総合考慮し、成年後見人による恣意(しい)的処分でなく、本人保護に資すると判断された場合に、家庭裁判所による許可の裁判がなされることになります。
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで本人の居住用不動産を売却した場合には、売買契約は無効です。
なお、本人の居住用不動産については、売却のほか、賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、抵当権の設定やこれらに準ずる処分をする場合にも、家庭裁判所の許可が必要です(859条の3)。
高齢化社会を迎え、成年後見の制度が利用されることが多くなっています。高齢者の財産処分に関する業務は、これから宅建業者にとって更に重要な業務になってきますから、成年後見の制度についても、十分に理解しておかなければなりません。